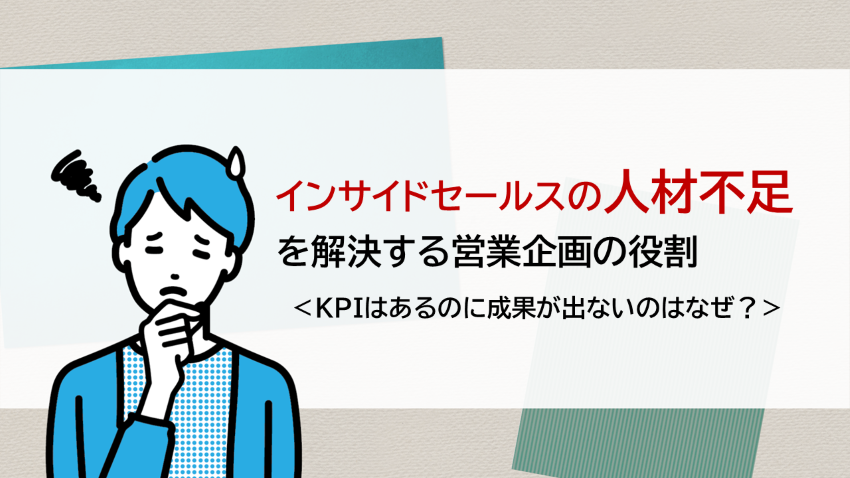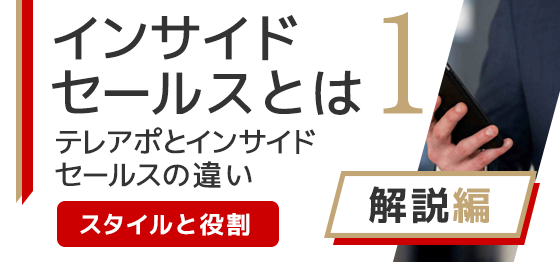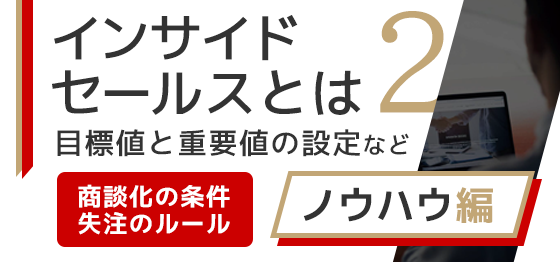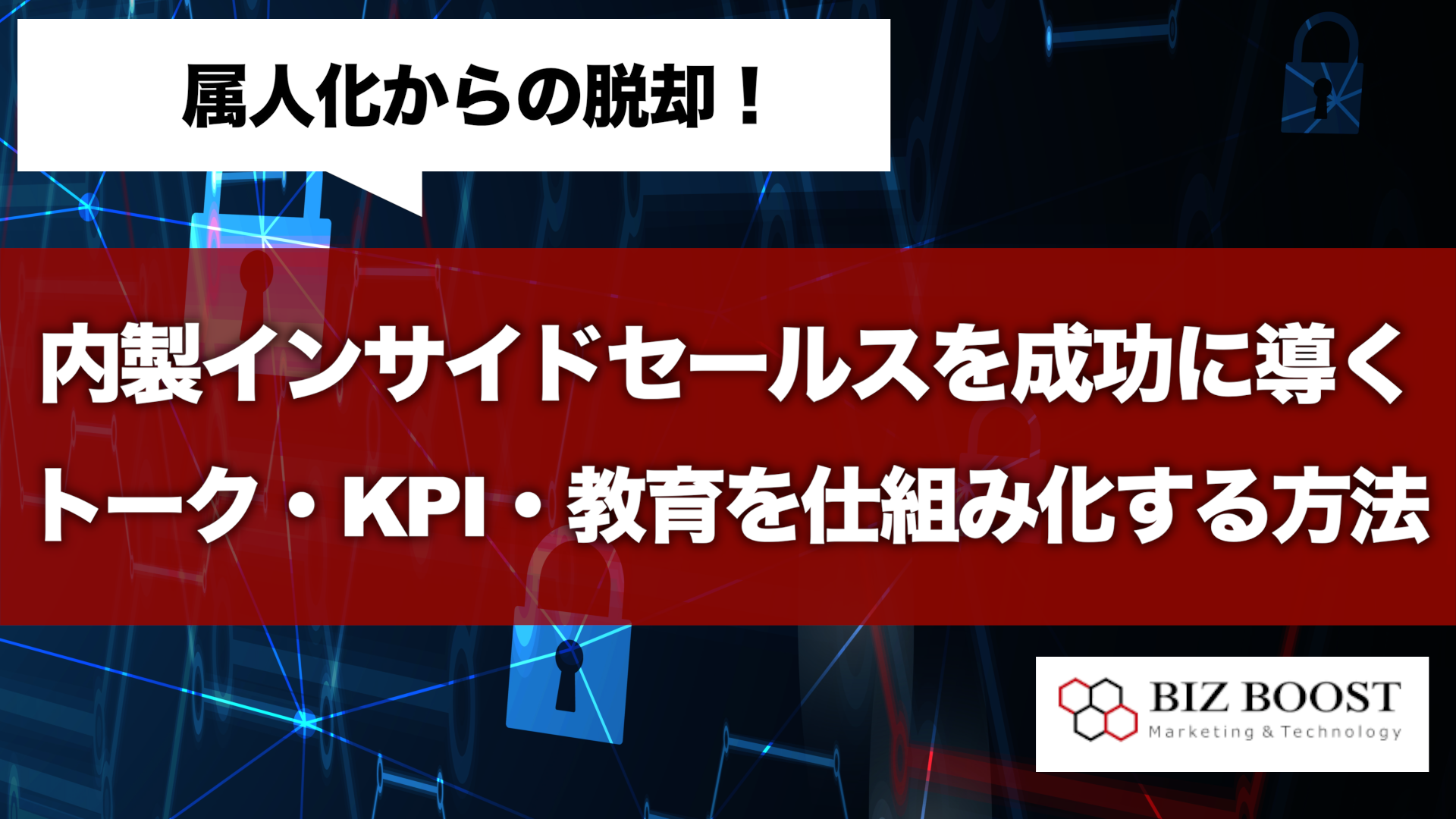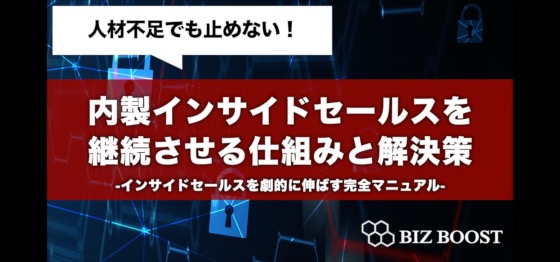インサイドセールスは、「行動量」だけでは成果が出ない時代になりました。
特にIT・SaaS・クラウドサービス業界では、見込み顧客との接点を持つインサイドセールスが事業成長の生命線と言っても過言ではありません。しかし、多くの企業が「インサイドセールスを内製化したが、人材不足で成果が頭打ちになっている」という悩みを抱えています。
「毎日一生懸命架電しているのに、質の高い商談につながらない」
「ベテランに頼りきりで、新人育成がうまくいかない」
「部門間で責任を押し付け合い、誰もが疲弊している」
もし、このような状況に心当たりがあるなら、それは「人の問題」ではなく、「組織の構造的な問題」である可能性が高いです。
この記事では、インサイドセールスの成果が出ない根本原因を解き明かし、営業企画部が主導してチームを再設計するための具体的な方法を解説します。人材を増やすのが難しい今だからこそ、設計の力で成果を最大化するヒントを掴んでください。
目次
1. なぜ「行動量KPI」だけでは成果が出ないのか?
多くのインサイドセールスチームは、架電数やアポイント獲得数といった行動量に焦点を当てたKPIを設定しています。しかし、これらのKPIを達成しても、商談化率や受注率が上がらないという壁にぶつかる企業が後を絶ちません。
この背景には、インサイドセールスチームにおける3つの「よくある誤解」が存在します。
誤解1:「行動量」を増やせば、自ずと「質」も向上する
架電数を増やすことは、確かにアポイント獲得の機会を増やします。しかし、量だけを追うと、質の伴わないアポイントが増加します。結果として、商談の途中で話が進まなかったり、受注に至らなかったりする「不毛な商談」が横行し、営業リソースを無駄にしてしまいます。重要なのは、「質の高い商談」を創出することであり、そのためには「行動の質」を向上させる仕組みが必要です。
誤解2:インサイドセールスの育成は「現場任せ」で良い
インサイドセールスメンバーのスキルは、経験や個性によって大きくばらつきます。にもかかわらず、そのスキルが可視化されていなかったり、統一された育成プログラムがなかったりする企業は少なくありません。結果として、成果は一部のベテランに依存し、チーム全体のパフォーマンスが向上しない属人化が進んでしまいます。
誤解3:部門間連携は「定例会」を開けば十分
マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスの各部門は、それぞれが異なるKPIを追いがちです。「リード獲得数(マーケティング)」「商談化数(インサイドセールス)」「受注数(フィールドセールス)」といった各部門の最適化だけを追求すると、部門間で責任を押し付け合う事態に陥ります。
例えば、インサイドセールスは「マーケティングが渡すリードの質が悪い」と不満を述べ、フィールドセールスは「インサイドセールスが設定する商談の質が低い」と指摘する…といった負のスパイラルが生まれます。
これらの問題は、現場の努力や個人の能力に依存する解決策だけでは不十分です。なぜなら、これらはすべて「組織の構造」に起因するからです。
2. なぜインサイドセールスの「構造設計」は営業企画が担うべきなのか?
多くの企業で、インサイドセールスの運用責任は営業やマーケティング部門に属し、営業企画は関与しづらい構造になっています。しかし、先に述べた課題の根本原因は、KPIやプロセス設計の問題であり、これらを事業全体を俯瞰して設計できる営業企画部門こそが、本来担うべき領域です。
営業企画がもたらす「全体最適」の視点
インサイドセールスは、単なる営業プロセスの一部ではなく、事業全体の成長を左右するハブです。マーケティングが獲得したリードを営業に繋ぐ「結節点」として、その機能不全は事業全体の成果に直結します。
営業企画は、個々の部門のKPIだけでなく、事業全体の「商談創出数」「受注率」「顧客LTV」といった指標をモニタリングし、全体最適な視点で課題を特定できます。この俯瞰的な視点こそが、部門間の対立を解消し、組織全体としてのパフォーマンスを最大化するために不可欠です。
イ
3. 営業企画が着手すべき「構造設計」3つのポイント
人材不足という制約がある中で成果を出すためには、個人の能力に依存しない「仕組み」を構築することが不可欠です。営業企画として、以下の3つのポイントに構造的に着手しましょう。
ポイント1:KPIをプロセス分解し、「中間指標」を再設計する
架電数やアポイント数といった最終的な行動量KPIだけでなく、そこに至るまでの中間指標を細かく設定し、分析することが重要です。これにより、ボトルネックがどこにあるのかを特定できます。
KPIの再設計例
- 商談化率:インサイドセールスが創出した商談が、フィールドセールスによって「有効商談」として認められた割合。
- アポイント獲得率:架電数に対するアポイント獲得数の割合。
- フォローアップ回数と商談化率の相関:商談が成立するまでの平均フォローアップ回数を計測し、非効率なフォローが多発していないかを分析します。
- リードソース別の商談化率:どのマーケティング施策から獲得したリードが商談に繋がりやすいかを分析し、マーケティング戦略にフィードバックします。
- 商談までの滞留日数:リード獲得から商談に至るまでの平均日数を可視化し、非効率なプロセスがないかをチェックします。
これらの指標をCRMやSFA、BIツールなどを活用してダッシュボード化することで、日々の活動を「見える化」できます。これにより、単なる「頑張れ」という精神論から脱却し、プロセスを改善するための具体的な打ち手を講じることが可能になります。
ポイント2:インサイドセールスの「スキル見える化」と「運用の標準化」
成果の属人化を防ぐには、スキルの可視化と運用ルールの標準化が欠かせません。営業企画が主導して、以下のツールや仕組みを導入しましょう。
- スキルマップの作成
メンバーごとのスキルレベル(例:ヒアリング力、課題特定力、提案力など)を客観的に評価し、見える化します。スキルマップの作成は以下のステップで進めます。
- 評価項目の設定: インサイドセールスに必要なスキル要素を具体的に定義します。
- 評価基準の策定: 各項目を5段階などで評価するための明確な基準を作成します。
- 定期的な評価サイクルの確立: 四半期ごとなど、定期的にスキルを評価し、メンバーにフィードバックする仕組みを構築します。
- ロールプレイチェックリストの導入
トークスキルやヒアリングの質を客観的に評価するためのチェックリストを作成し、育成に活用します。これにより、経験の浅いメンバーでも、質の高い会話を再現できるようになります。
- 成果を出すプロセスの「仕組み化」
個々の能力に依存せず、誰がやっても一定の成果が出せるよう、プロセス自体を仕組み化します。
- 型化されたスクリプトとトーク集の整備: ヒアリングの型、特定の課題に対する回答例など、トークスクリプトを整備し、チーム全体で共有します。
- リード優先度定義とスコアリングの仕組み: マーケティング部門と連携し、商談に繋がりやすいリードを定義します。その優先度に応じてインサイドセールスがフォローすべきリードを明確化することで、効率的な活動が可能になります。
- ナレッジ共有の仕組み化: 成功事例や失敗事例、顧客からのフィードバックなどを共有するためのツール(社内Wiki、チャットツールなど)を整備し、組織全体の知見として蓄積します。
ポイント3:KPIを軸とした部門間連携の再構築
インサイドセールスが最高の成果を出すためには、マーケティング部門やフィールドセールス部門との密な連携が不可欠です。営業企画がこの連携のハブとなり、以下の取り組みを進めましょう。
- 共通のKPIで「全体最適」を図る
各部門が「自部門のKPI」だけを追うのではなく、「有効商談数」「受注率」「平均商談単価」といった事業全体の成果に直結する共通のモニタリング指標を定めることが有効です。
- マーケティング: リード獲得数と、そのリードが有効商談に繋がった数。
- インサイドセールス: 有効商談数と、その商談が受注に繋がった数。
- フィールドセールス: 受注数と、その商談元となったインサイドセールスの貢献度。
このような共通指標を軸に連携することで、部門間の責任の押し付け合いを防ぎ、組織全体で課題解決に取り組む文化を醸成できます。
- 連携強化のための定例会
共通KPIをモニタリングするための定期的なミーティングを設けましょう。議論すべき具体的な議題は以下の通りです。
- 「今週の有効商談数が低い」→ 原因はリードの質か、インサイドセールスのプロセスか?
- 「受注率が低い商談に共通する特徴は?」→ インサイドセールスのヒアリング項目に漏れはないか?
- 「失注した商談の共通原因は?」→ マーケティングの訴求内容と商談内容にギャップはなかったか?
このような建設的な議論を定期的に行うことで、部門間の信頼関係が深まり、課題解決のスピードが格段に向上します。
4. 成功事例から学ぶ「構造変革」のポイント
仕組みを導入するだけでなく、それを組織に定着させるための「組織変革」の視点も重要です。
失敗事例:「とりあえずツール導入」で終わったケース
A社では、インサイドセールスの効率化を目指し、SFAを導入しました。しかし、KPIや運用ルールが曖昧だったため、現場はデータを入力するメリットを感じられず、活用が進みませんでした。結果として、ツール導入に費やした費用と労力は無駄となり、成果は改善しませんでした。
成功事例:「ロードマップ」に基づき段階的に進めたケース
B社では、営業企画が主導し、インサイドセールスの構造変革を以下の3ステップで進めました。
- 現状分析と共通KPIの定義: まずはマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスの各KPIを洗い出し、事業全体の成果に直結する「有効商談数」を共通KPIとして定義しました。
- 運用ルールの標準化: スキルマップとトークスクリプトを作成し、個人のスキルに依存しない「型」を構築しました。
- 仕組みの定着と改善: 定期的なミーティングを通じて共通KPIをモニタリングし、ボトルネックを特定して改善サイクルを回しました。
このロードマップに従い、段階的に仕組みを導入することで、現場の反発を抑えつつ、組織全体での変革を成功させました。結果、インサイドセールスの商談化率は30%向上し、人材不足という課題を抱えながらも、事業成長を加速させることに成功しました。
5. まとめ:人材不足は「設計」で補える
「インサイドセールスの人材不足」は、一朝一夕に解決できる問題ではありません。しかし、営業企画が「現場の頑張り」に依存するのではなく、インサイドセールスチームの構造そのものを見直すことで、限られたリソースでも劇的に成果を改善できます。
今回の内容をまとめると、以下の3つのポイントが重要です。
- KPIの再設計:行動量だけでなく「中間指標」を細かく設定し、ボトルネックを特定する。
- プロセスの仕組み化:スキルを見える化し、運用ルールを標準化することで属人化を防ぐ。
- 部門間連携の再構築:共通のKPIを軸に、全体最適な組織を設計する。
あなたの企業が抱えるインサイドセールスの悩みは、もしかすると「人の問題」ではなく、「構造の問題」かもしれません。
ぜひ、この機会に営業企画の視点からインサイドセールスチームの設計を見直し、再現性の高い組織を作り上げていきましょう。
インサイドセールスの成果を最大化する「構造設計」を専門家と進めませんか?
ビズブーストは、BtoB企業のインサイドセールス組織設計を専門としています。
人材不足の課題を抱える企業様向けに、KPI設計から運用体制の構築、スキル標準化まで、貴社の状況に合わせた最適な「仕組み」づくりを支援します。
もし、この記事で解説したような「構造的な課題」に直面しているようでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社のインサイドセールスを「成果を出す組織」へと変革しませんか?
- 成果を出すインサイドセールス組織を内製化したい方はこちら
• デジタルインサイドセールスコンサルティングの詳細を見る - リソース不足を解消し、即座に質の高い商談を獲得したい方はこちら
• インサイドセールス代行サービスの詳細を見る
インサイドセールスの資料ダウンロードはこちらから



.png)