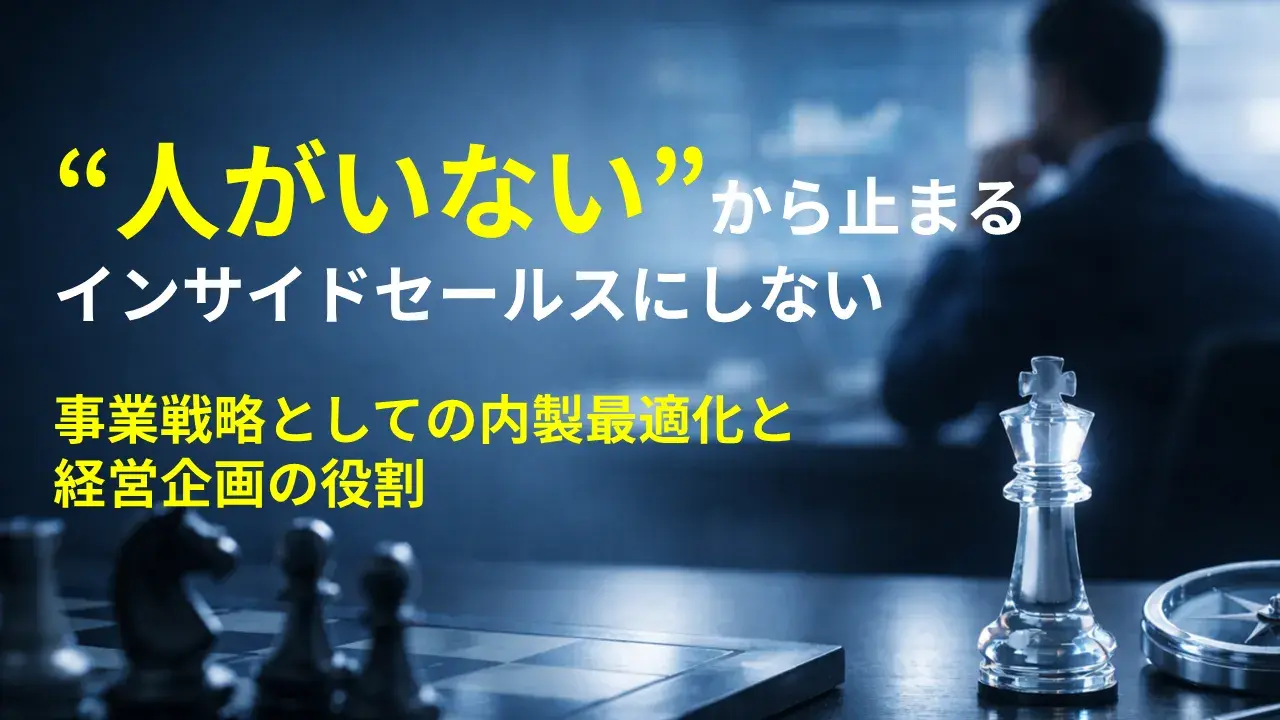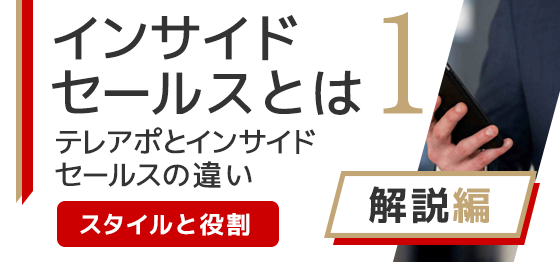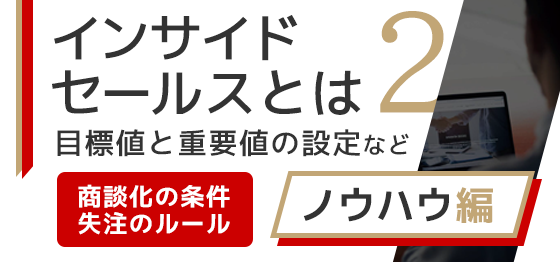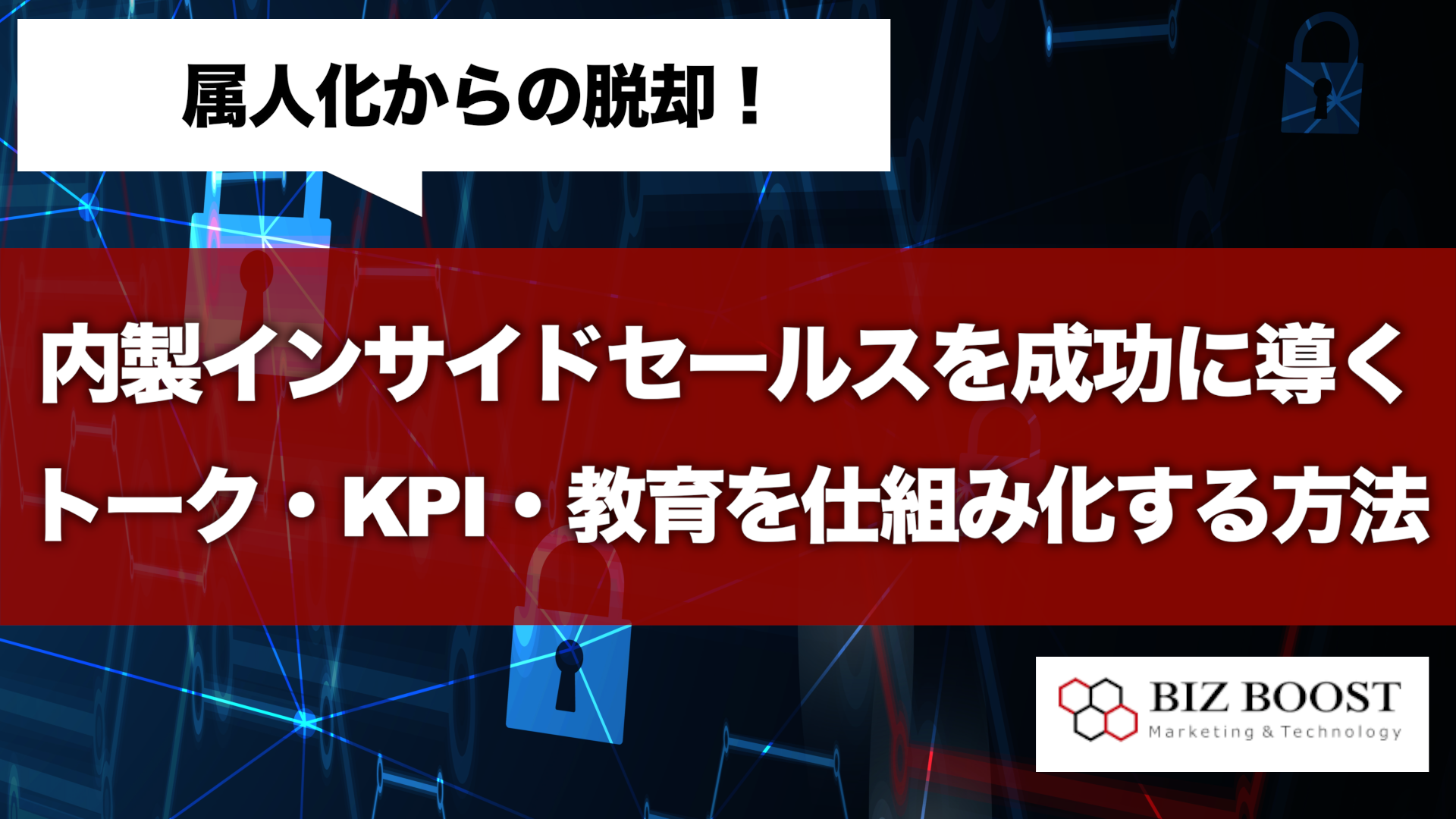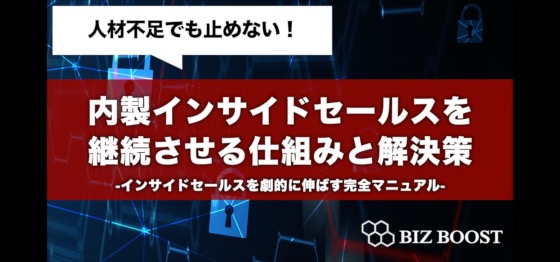現在、多くのIT・SaaS企業が事業成長の要としてインサイドセールスの内製化を進めています。しかし、その多くが「人材が足りない」「採用がうまくいかない」「人が定着しない」という課題に直面し、せっかく立ち上げたインサイドセールス組織が機能不全に陥っています。
「また採用の目標未達か…」「予算をかけたのに、商談数が頭打ちになっている…」
経営会議の場で、営業部門からの報告を聞きながら、あなたはそう感じていませんか。インサイドセールスを「電話をかけるだけの部隊」と見なし、適切な投資や戦略的な設計を怠れば、その組織は単なるコストセンターとなり、いずれ機能不全に陥ります。
この問題は、単なるリソース不足ではなく、インサイドセールスを「事業成長の中核」として捉え、経営視点で戦略的に設計・運用できていないことが根本的な原因です。本記事は、インサイドセールス内製化の課題に直面している経営企画部の皆様に向け、人材に依存しない、持続可能な営業モデルを構築するための具体的な視点と役割について解説します。
目次
1. インサイドセールスは“営業の一部”で終わらせてはいけない
インサイドセールスは、見込み顧客へのアプローチから商談機会の創出までを担う、現代の営業活動において不可欠な機能です。しかし、多くの企業ではインサイドセールスがフィールド営業のサポート役、あるいは営業部の下請けのような位置づけで終わってしまっています。
このような体制では、インサイドセールスは部分最適の機能となり、全社的な事業成長に貢献する戦略的な役割を果たすことができません。インサイドセールスは本来、マーケティングが創出したリードを効率的に商談へと変換し、事業成長の源泉となる商談創出の「生産装置」と捉えるべき存在です。
この「生産装置」をいかに効率良く稼働させ、事業KPIに直結させるかという視点が、インサイドセールスを内製化する上での出発点となります。
2. 内製化したインサイドセールスが「人材不足」で失敗する3つの共通点
なぜ、多くの企業でインサイドセールス組織が人材不足によって立ち行かなくなるのでしょうか。そこにはいくつかの共通点があります。
1. 採用・育成・運用の悪循環モデル
現場起点で始まったインサイドセールス組織は、多くのケースで属人的な運用に陥ります。
- 採用の失敗: 「インサイドセールスの経験者」という曖昧な要件で採用活動を行う。
- 育成の未整備: 教育体制がなく、OJT(On the Job Training)に依存するため、個人のスキルに成果が左右される。
- 成果の不安定: 一部の優秀なメンバーに依存し、組織全体のパフォーマンスが安定しない。
- 高い離職率: 適切な評価制度やキャリアパスがなく、メンバーが将来を描けず離職する。
この負のループが続くと、新規採用はさらに困難になり、「人がいない」という根本的な問題が加速していきます。特に100~500名規模の中堅企業では、ブランド力や採用リソースの面で大手企業に劣るため、この問題はより深刻です。
2. 全社戦略と紐づかないKPI設定
インサイドセールスが追うべきKPI(例:架電数、商談数)が、フィールド営業の都合や短期的な成果指標に偏っていることがあります。これにより、インサイドセールスがどれだけ成果を出しても、それが事業全体の受注率やARR(年間経常収益)向上にどう貢献しているのかが不明瞭になります。
例えば、「商談数を増やす」というKPIを追求した結果、商談の質が軽視され、最終的な受注に繋がらない「無駄な商談」が増加するケースが典型です。インサイドセールスは「アポ取り屋」と揶揄され、フィールド営業からは「質の悪い商談ばかり」と不満が出る。組織間の対立が生まれ、事業成長の妨げとなります。
3. 投資対効果(ROI)の曖昧さ
インサイドセールスは「コストセンター」と認識されがちですが、本来は投資対効果を明確に算出し、事業成長への貢献を可視化すべき「プロフィットセンター」です。しかし、多くのケースで、そのROIが曖昧なまま運用され、経営層からの理解を得られず、組織の存在意義が社内で揺らいでしまいます。
インサイドセールスへの投資が、顧客獲得コスト(CAC)をどの程度削減し、事業全体の売上をどれだけ向上させているのかを明確に説明できない限り、インサイドセールスは単なる「コスト」でしかありません。
(関連記事)
▼展示会で得たリード、そのままにしていませんか?人材不足を乗り越え、成果を出すインサイドセールス再設計の全貌
3. 経営企画が担うべき“戦略的インサイドセールス支援”のあり方:実行のための7ステップ
事業成長のエンジンとなるインサイドセールスを構築するためには、現場任せではなく、経営企画が中心となって「設計」と「最適化」を主導していく必要があります。
ステップ1:現状分析と営業活動の「健康診断」
まずは、インサイドセールスを含む営業活動全体の現状を客観的に把握します。
- KPIの定義と分析: リードソース別の商談化率、有効商談数、商談からの受注率、平均受注単価、営業サイクルタイムなど、定量的なデータを収集・分析します。
- ボトルネックの特定: どのフェーズで商談が滞留しているのか、どのリードソースからの商談が最も受注に繋がりやすいのかを特定します。
- 現場へのヒアリング: インサイドセールス、フィールド営業、マーケティングの各担当者から、現状の課題や不満点をヒアリングし、定性的な情報を収集します。
ステップ2:インサイドセールスの役割とKPIの再定義
インサイドセールスを「アポ取り」という単純な役割から解放し、事業戦略に沿った役割を再定義します。
- 役割の拡張: 単なる商談創出だけでなく、「リードナーチャリング(顧客育成)」「既存顧客へのアップセル・クロスセル」といった役割もインサイドセールスが担うことで、事業全体のLTV(顧客生涯価値)向上に貢献するモデルを検討します。
- 事業KPIと紐づいた指標設定: インサイドセールスの活動指標(例:有効商談数)を、最終的な事業KPI(受注件数、ARR、LTVなど)に紐づけます。これにより、インサイドセールスが事業成長にどれだけ貢献しているかを明確に可視化できます。
ステップ3:「人に頼らない」生産性構造の設計
人材不足が避けられない現状を前提に、「人」に依存しない仕組みを構築します。
- プロセス設計とデータ活用: 属人的なスキルに頼るのではなく、顧客セグメントごとのアプローチ方法やトークスクリプトを標準化します。また、CRM/SFAへの活動履歴の入力を徹底させ、そのデータをナレッジとして活用できる仕組みを構築します。
- MAツールとの連携強化: マーケティングオートメーション(MA)ツールでスコアリングされたホットリードを、自動的にインサイドセールスにアサインする仕組みを構築します。これにより、営業効率を最大化し、インサイドセールスは質の高いリードに集中できます。
- AI・音声解析ツールの導入: AIによる架電内容の自動文字起こしや、トークの改善点をフィードバックするツールの導入を検討し、メンバーのスキルアップを支援します。
ステップ4:ハイブリッド型組織の設計と外部パートナーの活用
インサイドセールスの全てを内製するのではなく、外部パートナーの活用も視野に入れます。
- 戦略的外注: 「人材がいないから外部に頼る」という安易な発想ではなく、「何を内製し、何を外注するか」の戦略的判断を下します。
- 例:「初期の立ち上げ期はノウハウを持つ外部パートナーに任せ、一定の型ができてから内製化を進める」
- 例:「コールドリードへのアプローチは外部に任せ、インサイドセールスはホットリードに集中する」
- ハイブリッドな体制の構築: 外部パートナー、テクノロジー、そして内製のコアメンバーが連携するハイブリッドな営業モデルを設計します。
ステップ5:人材育成・評価制度の再構築
インサイドセールスメンバーが安心して働ける環境を整備します。
- 明確なキャリアパスの提示: インサイドセールスが単なる通過点ではないことを示すため、インサイドセールス→フィールド営業→マネージャーといった明確なキャリアパスを提示します。
- 公平な評価制度: 「商談数」だけでなく、商談の質や顧客への貢献度、CRMへの入力状況といったプロセスや行動を評価に組み込みます。
ステップ6:投資対効果(ROI)の可視化と社内共有
インサイドセールスへの投資が、事業にどれだけ貢献しているかを具体的に示します。
- 具体的な指標のモニタリング:
- 商談1件あたりの獲得コスト(CAC)
- インサイドセールス経由の商談からの売上(ARR)
- インサイドセールスが生み出した商談の受注率
- 経営陣へのレポート: 四半期ごとにこれらの指標を経営陣にレポートし、インサイドセールスがプロフィットセンターであることを証明します。これにより、インサイドセールスへの継続的な投資を促すことができます。
ステップ7:組織間のコミュニケーション設計
インサイドセールスとフィールド営業、マーケティング部門との間に構造的な連携をデザインします。
- 定例ミーティングの仕組み化: 部門間の定例ミーティングを仕組み化し、商談の質に関するフィードバックや、新しいマーケティング施策の共有を行います。
- 共同の目標設定: インサイドセールスが創出した商談からの受注率を、フィールド営業の目標としても設定するなど、共通の目標を持つことで、部門間の連携を強化します。
(関連記事)
▼“育てて回す”インサイドセールス体制への転換を今なぜ経営企画が主導すべきか?分業営業の限界と再構築の戦略論
4. 成功事例に学ぶ、事業成長の「設計」
例えば、社員数150名のSaaS企業A社は、インサイドセールスの離職率が高いことに悩んでいました。経営企画部が主導し、上記のステップを踏んだところ、以下のような成果が出ました。
- ステップ1で分析: 質の低い商談が多く、フィールド営業からの不満が溜まっていることが判明。
- ステップ2で再定義: 「無駄な商談をゼロにする」という目標を掲げ、KPIを「有効商談数」に絞り込み。
- ステップ3で仕組み化: マーケティング部門と連携し、リードスコアリングの閾値を上げることで、インサイドセールスに渡すリードの質を向上。さらに、CRMへの入力ルールを厳格化し、ナレッジの蓄積を推進。
- ステップ4でハイブリッド化: コールドリードへのアプローチは外部パートナーに委託し、内製のインサイドセールスはホットリードに集中。
この取り組みにより、A社のインサイドセールスはメンバー数が変わらないにもかかわらず、商談からの受注率が20%向上しました。人がいなくても商談パイプラインが止まらない組織が構築され、年間売上は前年比150%を達成しました。
5. 結びに:事業の未来を拓くのは、現場の努力ではなく、経営の「設計」である
インサイドセールス内製化は、単なる営業効率化ではなく、事業の持続可能性を左右する経営判断です。「人がいないから回らない」という課題は、現場の努力だけで解決できるものではありません。これは「リソースに依存せず、いかに成果を出すか」という組織構造の設計判断であり、まさに経営企画がリードすべき領域です。
(関連記事)
▼“人がいないから設計できない”は本当か?営業企画が今こそ着手すべきインサイドセールスチーム運用設計の再構築
▼インサイドセールスの人材不足を解決する営業企画の役割 KPIはあるのに成果が出ないのはなぜ?
「人材が足りない」を経営戦略で乗り越える
ビズブーストにお任せください
本記事で解説した「戦略的なインサイドセールス組織」の構築は、多くの経営企画部の皆様にとって、多岐にわたる専門知識と実行力が求められるテーマです。
- 「何から手をつければいいか分からない」
- 「自社に最適なプロセス設計がイメージできない」
- 「データ分析やツール導入のノウハウがない」
もし、貴社がこのような課題を抱えているなら、ぜひ一度ビズブーストにご相談ください。当社は、SaaS・IT企業向けに特化したインサイドセールス戦略のコンサルティングと、質の高いリード創出を支援するサービスを提供しています。
貴社のインサイドセールスを「成果を出す組織」へと変革しませんか?
- 成果を出すインサイドセールス組織を内製化したい方はこちら
• デジタルインサイドセールスコンサルティングの詳細を見る - リソース不足を解消し、即座に質の高い商談を獲得したい方はこちら
• インサイドセールス代行サービスの詳細を見る
インサイドセールスの資料ダウンロードはこちらから



.png)